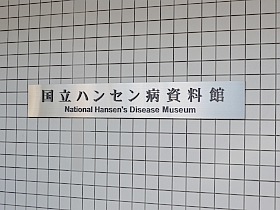

平成20年度 6月定例会
国立ハンセン病資料館見学
ハンセン病物故者追善法要
平成20年6月10日(火)、6月定例会を開催。千葉市海蔵寺にて梅花練習の後、東村山市 国立療養所多磨全生園(たまぜんしょうえん)へ移動。ハンセン病物故者追善法要を勤め、国立ハンセン病資料館を見学しました。
最初に行った梅花練習では庄司徳潤師が講師を務め、「同行御詠歌」を練習しました。詠讃歌とは、御詠歌・御和讃・讃歌の3つの総称です。御和讃が七・五の2〜6句からなる曲であるのに対し、御詠歌は五七五七七の短歌の形をとっており、和讃に比べて節回しが複雑になっています。定例会で御詠歌を練習するのは今回が初めてのため、梅花初心者の会員は特に大変そうでしたが、皆熱心に練習していました。
約30分の練習を終え、一同はバスに乗って多磨全生園へ。
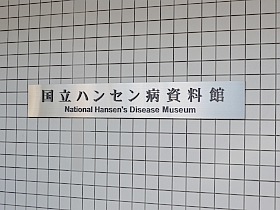

多磨全生園は、全国に15ヶ所あるハンセン病療養施設の1つです。「ハンセン病」とは、らい菌が皮膚や末梢神経等に寄生することによっておこる慢性の感染症で、発病すると皮疹や知覚麻痺、視力障害等の症状がみられますが、この病気自体で死亡することはほとんどありません。また、この菌の繁殖力は弱く、健康な人であればまず感染しません。感染しても発病することは滅多になく、1943年に開発されたプロミンはじめ化学療法剤によって、確実に治る病気となりました。(※ハンセン病についての詳細はこちらをご参照ください。)
ところが、昔は病気の原因が分からなかったため有効な治療法もなく、特徴的な後遺症(感染箇所の変形等)などから、「不治の病」「恐ろしい伝染病」などと忌まれてきました。さらに、昭和28年に施行された「らい予防法」により感染者は全員強制的に収容されることになってしまい、故郷に帰ることも許されず、一生を療養所で過ごすしかありませんでした。
この法律は平成8(1996)年に廃止され、入所者は療養所を出ることも、療養所外で就職することも可能になりました。しかし、平均年齢が80歳近くであること、生活習慣病等の合併症を有している方が多いことなどから社会復帰は難しく、さらに社会的な偏見や差別は未だに根強く残っています。
園内には納骨堂が有り、故郷に帰ることの出来なかった4千体近くのご遺骨が安置されています。われわれは納骨堂前で供養の法要を勤め、ハンセン病や療養所について正しく理解するために、国立ハンセン病資料館を見学しました。


国立ハンセン病資料館は、平成5年に「高松宮記念ハンセン病資料館」としてオープンしたもので、資料館の拡充に伴い現在の名前となりました。展示室は3つに分かれており、それぞれハンセン病の歴史、過去の療養所内の様子、現在の状況、また海外のハンセン病事情についても知ることが出来ます。
入所者による講演(語り部活動)も行われており、今回は多磨全生園入所者自治会会長の佐川さんから、療養所やらい予防法が施行されてからの歴史、全生園の中での生活についてなどのお話をお聞きすることができました。治療の為の施設であるのに入所者は自分たちで協力して生活し、園内で働かなければならないこと、治っても出所できなかったこと、結婚できても子どもを生むことが許されなかったことなど、入所者は数々の不当な待遇に悲しみや怒りを感じることが少なくありませんでした。
佐川さんは講演の最後を、「薬剤治療のおかげで感染者はどんどん減っていき、療養所の入所者もゼロになる日が来るだろう。けれど、こういう病気があったこと、この病気のために、偏見のために、何十年と苦しめられてきた人がいることを後世に伝えたい」そして、「身体障害者、難病を煩っている方などに会ったら、思いやりの心で接してほしい」と締めくくられました。
ハンセン病に限らず、世の中には様々な差別、不当な待遇が存在します。それは、知識不足から来る恐怖、思いこみ、偏見、あるいは自分だけは不幸になりたくない、他人と比べて優れていると感じたい、など人の心の弱さが生み出すものです。今回の定例会でハンセン病に対する知識が深まり、間違った差別や偏見を無くしていこうと感じるとともに、自分自身が差別や偏見の心でものを見ていないか、あらためて省みるきっかけになりました。

●会長のコメント● 昔から人々は、科学的根拠のない迷信や通説、思い込みなどによる様々な差別や偏見を当たり前のように行ってきました。 |