








平成19年度 海外研修旅行
【3日目/2月28日(木)/担当:畠山賢陀】
【万里の長城】
2月28日。私は初めて万里の長城の上に立った。噂に違わぬ、壮大な建造物である。城壁は尾根伝いに果てしなく続き、内と外とを完全に分断している。6300キロもの長きにわたる城壁の上は、急斜面であることも珍しくなく、歩く者の呼吸を容赦なく乱す。
2000年もの昔、秦の始皇帝によって完成されたと言われるが、根源はもっと古い。侵入を繰り返す北方民族への対策として、中国側の王朝が築いたものとされる。
これは、壮大なる壁なのだ。
極論になるが、そもそも両者において仲が良ければ、壁などというものは必要ない。つまり雄然と残るこの壮大な城壁は、過去において両者の仲が良くなかったということを表す、負の証明物ということだ。
NO BORDER 少し前にそんなCMがあった。今となっては、ややうろ覚えではあるが、おおむね次の様なCMだった。
広い荒野の中央に、一本の線が引かれている。線のこちら側と向こう側とから、屈強な男たちが殺気に満ちた表情で詰め寄ってくる。手を出せばまさに届く距離で、両者はにらみ合う。しかしそこで、ふと視線を落とせば、線に見えたものは実は線ではなく、長く一列に並べられたカップラーメン。男たちはそれに手を伸ばし、食べる。食べることにより満たされた男たちは、いつしか戦う気も失せ、笑顔で肩を組み合う。
世の中には、そもそも境や壁などというものは必要のないものだ。肩を組み、笑いあって得られる喜びこそ、意地を張り合いや争いによって得られるものなどよりもずっと素晴らしいもの。「壁」などというものは、世界から、心から、新たに創ることなく、なくしていかなければならぬ。
世界には今まで、様々な壁があった。この万里の長城やベルリンの壁のように、今では不要となった壁もある。しかし一方で、まだ現役の壁もある。日韓・日中の一向に縮まらぬ心の壁、パレスチナにも壁があり、今日またイラクにおいても、宗派間の抗争を避ける為とはいえ新たな壁が構築された。
我々は歴史に何を学ぶのか。この壮大な遺産、負の証明物が語りかけてくるのは、単に歴史的・文化的側面のことだけではないはずである。
仲良きことこそ、美しきかな。壁で隔てていがみ合うよりも、よほど良いことだと思うのだが、それは人類として理想論に過ぎないのだろうか。たとえ理想論にすぎないとしても、それを願わずにおれないのが、人というものではなかろうか。
海が海たりえるのは、そこに流れ込む川の水を、たとえ異質なものであっても、すべて受け入れ続けるからだ。道元禅師の言葉も、今日いまだなお届ききらず。我々の胸の内にこだまし続ける。









【鳥の巣】
私たちの宿泊したホテルは、北京オリンピックのメイン会場となる通称「鳥の巣」の目と鼻の先。ホテル内部や周辺は、とりわけ国際色豊かに感じ、また治安面でも特別に不安を感じることはありません。
ただ私が感じたところでは、ホテル内はいわば「作り物の中国」ないしは「厚化粧の中国」という印象。様々な面で「アピール用に」為されている印象がぬぐいきれませんでした。


【居庸関】
辺境から北京に至る街道筋の所々には、「関」つまり「関所」がある。三国志などの物語にも当時の交易や防衛上の要衝として幾度となく出てくる存在である。長城から北京へ戻る道すがら、立ち寄ることができたのが居庸関(きょようかん)という関。現在使用されている訳ではないが、物語そのままの姿を目の当たりにして、ささやかな感動を覚えた。

【七宝焼きの工場】




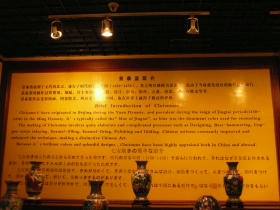
【食事】
毎回毎食、とにかく量が多い。山盛りの料理が何皿も出されてくる。私たち日本人は、出されたものは綺麗に頂くのが礼儀にかなっていることだと考えるが、聞けば中国ではそうではないらしい。平らげてしまうと「美味しかったけれど、量が足りませんでした」という意味になってしまい、却って失礼に当たるのだとか。なるほど、ところ変われば随分違うものだ。
人は、他人の行為を見ても、己の物差しで善悪をはかってしまい、時に断罪までしてしまう。しかしお互いのそんな「正しいことの物差しの違い」を、お互いにもっと興味を持って聞くことができれば、そこから相互理解へと発展していけるようにも思う。
とか何とかいいながら、美味しいのでどんどん食べてしまった私は、帰国後まもなくやってくる青年会の次の行事「人間ドック」への影響を心配せずにはおれなくなっていった。

【定陵】
明の歴代皇帝が葬られているという場所。地形に合わせ、各所に皇帝の陵墓が存在する。つまりここは中国版「王家の谷」のようなところ。中国の皇帝は、自分の陵墓が完成すると、自分の死後の家として大勢の人を集めて披露したのだそうです。





【中国雑伎団】
中国といえばこれ。現地ガイドさんと運転手さんの腕か、移動が実にスムースだったため、時間的余裕が出来て実現したのが、中国雑伎団見物。予定外のことなので、各自で追加料金を支払いましたが、期待どおりの素晴らしい演技で満足のいくものでした。
席はAとBと2種類あり、私たちは前の方のA席を取ってもらいました。少し料金は増すが、一生に幾度もあることでもない上に、AとBの価格差はそれほど大きくないと感じたからです。しかし席についてみて驚きました。A席は見事に私たちを含む外国人ばかりだったのです。早くから来て開演を待つ中国人も大勢いましたが、みな後方のB席。A席に、まるで羨望の眼差しが注がれている様な、妙な居心地の悪さを感じました。ただ雑伎団自体がおそらく娯楽のものでありましょうから、来ている中国人も困窮している人たちではないとは思うのですが、それでもこれだけはっきりと分かれていると、考えさせられました。
中国に来てずっと感じていたことは、経済的な意味で、諸外国また国内における格差。華やかな北京の、ほんの一区画先には胡同(ふーとん)と呼ばれる旧市街が広がっていたり、寺院の近辺には物乞いの姿も見える。北京を一歩出て見れば、華やかな町並みはいっぺんに消え、荒涼たる荒野が広がるのみ。華やかな輝きにかき消されがちな中に、捨ててはおけない現実の中国の姿があるように感じました。


強く印象に残ったのは、夜にホテル外に出て街中を歩き、「一般市民が利用する普通の」お店などに行ったこと。空気も物価も、やはりホテル内とは全く異なるもので、「これこそが中国なのだ」「これが中国なのだ」という実感を得、初めて「素顔の」中国を感じました。私にとって、これこそが今回の研修旅行の中で最も大きな収穫。もう少し言葉と時間が自由ならば、このあたりをもっと深めて行きたかったところです。